人前で消えてしまいたかった経験
僕が中学1年生の時、学校の集会場にて全校生徒の前で、夏休みの自由研究か何かの成果を発表する機会がありました。その時になるまで、発表は普通にできると思っていました。例えば、授業中などに発表することは特に苦ではなかったので、その延長でできるだろう程度にしか考えていませんでした。しかし、いざ全校生徒の前でマイクを握ると、しゃべっているうちに声がか弱くなり、消え入りそうになり、ついには自分自身もそこから消えてしまいたい感覚に襲われました。緊張は緊張でも、消えてしまいたいとまで思った感覚を大人になっても克明に覚えています。あれはなぜ起きたのだろうか、と考えてみました。

緊張や萎縮も加わって…
大学に入ってゼミでの発表の機会や、大人になって会議などでの発言の機会などがあり、それはそれで人並みにやり過ごしてはいましたが、どこか心はふわふわしています。単なる緊張というものでは説明がつかない違和感がずっとありました。併せて自分でも気になっていたことは、仕事で初対面の人とお会いするとき、緊張したり萎縮したりすることでした。すぐに打ち解けている同僚や先輩、後輩などをみるたびに、自分は人付き合いに向いていないのだろうかと気を落としました。人と気楽に楽しく付き合っていける方が、仕事も進めやすいし、新しい契約も成立しやすいに違いありません。人前で緊張したり萎縮したりしない自分になりたいと思っていました。それは場数ではなかったのです。
場数という意味では、たくさん経験をさせてもらったと思っています。自分が前に出なければ仕事にならないという環境が長く続きましたので、とにかく毎日のように人と会い、初めましての方もその中には含まれていました。人と会うことに力まずに慣れたと思えたのが30代半ばくらいですが、慣れたら慣れたで、次は目上の方の前では萎縮をしたり、逆に人に対して威圧的になったりする自分が目立ってきました。「なぜ自分は、こうなんだろう」と自分が自分で嫌になっていました。
「上下関係」というメガネ

その理由は、自分自身が人と人との関係を上下に見ていることにあると知ったのです。それは、自分の幼少期からを振り返った時に、実に合点がいきました。親子関係が上下関係だったのです。親の指示命令に従順な子どもでしたし、そうすることで機嫌を損なわない親でいて欲しいと願っていたということもあります。怒ったり機嫌を損ねたりしている親は、自分のことを拒絶している姿に思えて、本当に嫌でした。ですから、僕は常に親の顔色を伺い、親の要求することに従い、期待に添うように生きようと努めてきました。
「子どものため」というカムフラージュ
親の要求と言っても、従順な子ども/無批判な子どもからすれば、それは自分のためを思って言ってくれていることとしか思っていませんでした。勉強をしろ、口には出さずとも、遊びを優先しているといい顔をしない親、部活動で遅くなるといい顔をしない親も同じことです。子どもの優先したいこと、没頭したいことに理解を示さない親です。「将来、あなたが困らないように」という一言で、全ては正当化され、子どものためを思っての言動だと信じていました。しかし、それは、親自身の精神の未成熟だと言えます。目の前の子どもの気持ちを聞いてやれないのです。「言う通りにしろ、そうでないと私が不安なのだ。私の方が正しいのだ」。これが精神の成熟した大人だと言えるでしょうか?
親は親で、自分が言う通りに子どもが従うと、それで子どもが成長すると信じているのです。その親自身がそのように育ってきたのでしょう。その是非を自分で振り返らないまま、我が子にも同じようにしようとしても、子どもは全く別の人格を持った人間ですから、同じように聞き分けよく育つとも限りません。まずは、目の前の子どもをしっかりと観察し、子どもの気持ちを聞いてやることが第一なはずです。それをせず、子どもの気持ちを抑圧し、自分の主張を黙っている子どもに押し付け、従わせる。この関係性が上下関係です。親子関係が上下関係であれば、大人になっても全てに人間関係は上下関係になってしまいます。
フラットな関係性が自然な姿
人と人は、本来はフラットな関係です。上下関係には、権力や地位、時に金といった世界とも近いように思われます。権力のある人が上、金にものを言わせる人は金があれば立場が上。そういう発想では、豊かな人間関係を築くことはできません。僕は上下関係で人を見ていたから、自分よりも地位の高い人の前では萎縮をし、権力の前に跪き、金持ちを色眼鏡で見ていたのだと気づきました。その原点は、やはり親子関係でした。

上下から対等に変えるために
上下を対等に変えていくには、親の前で緊張し、萎縮をしていた時点まで戻り、その自分を解放するところから始めなくてはなりません。つまり、自分の素直な気持ちを言うことを習慣にしていくことです。これを言うと親は機嫌を損ねるかな?これを言うと親は怒るかな?そう思って萎縮し、緊張し、抑圧していた心を開くことからスタートです。
そうは言っても、まだ自分の素直な気持ちを口にすることに関しては、よちよち歩きのヒヨコ同然です。自分の素直な気持ちをぶつけて、拒否られたり、自信を無くしたりする経験があると、そのハードルはとても高いと思います。最初は、誰に言うかに慎重になることも大切です。
・信頼できる人にぶつける
・自分で自分の気持ちを受け止める
・人に言わなくても、自分にだけは嘘をつかず、自分の本音を掴んでおく習慣をつける
このようなことから始めるのが良いと思います。
人に言えないけど、自分で本音を掴むならやってみたい!と思える人には、you tubeで有料プログラムをご案内できるよう、準備中です。
さらに!
それができれば、抑圧をされたと感じている人(例えば親)の背景に思いを馳せることです。なぜあの人は、自分を抑圧をしたのだろうか。そう思うと、その人の心の闇に気づきます。例えば、親自身が子どもの精神性のままだということがあります。親自身も、自分の親からの愛情をいまだに求めている場合、それはもはや叶わないとわかっていても、その代償行為として人から褒められたい、認められたいという気持ちを満たそうとします。子どもの頃に満たされなかった親からの愛情のバケツが満たされないまま、親離れできずにこじらしていることがあります。その幼児性を子どもに向けてしまうと、子どもを利用して「自分の子育ては凄いだろう!」と主張することもできます。そういうふうにされた子どもは、上下関係に縛られた子どもです。
自分の親もまた、子どもの精神性のまま大きくなったのだ、自分と同じじゃないか。親の持つ弱さを、自分も持っているじゃないか! 例えば、人前で萎縮し、逆に人を見て威圧的になるなどですね。そう思えた時に、「同じ人間」として対等に思えてきます。そこまで感じられると、上下関係で結ばれていた親子関係も、真に対等だと更新できると思います。この「対等な感覚」が、人前で自信を持って喋ることのできる根本であり、本質だと思います。
まとめ
人前で自信を持って喋ることは、小手先のテクニックなどではなく、上下関係によって人に心を閉ざしていたからなのです。その心を開くには、上下関係を対等な関係に変えていくしかないのだと思います。
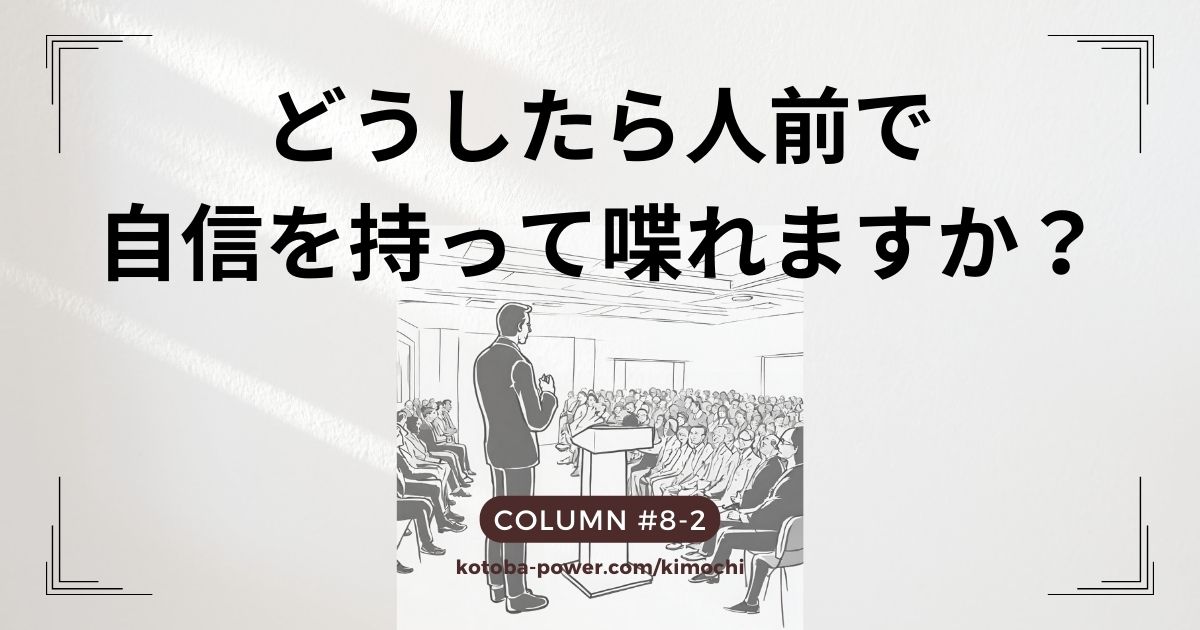

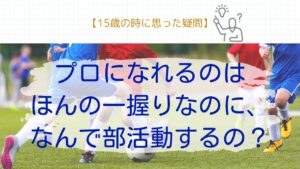

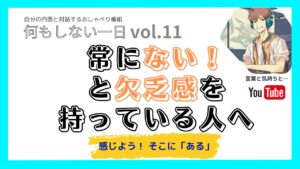
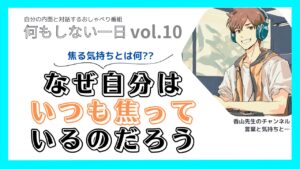
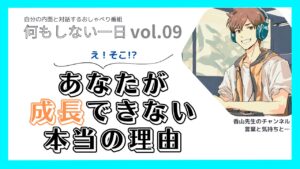
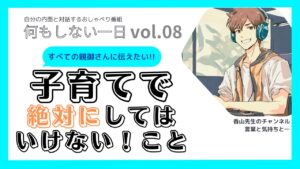
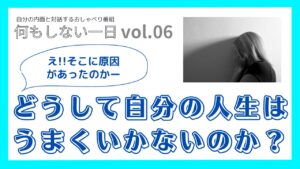
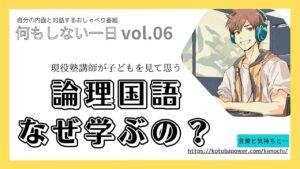
コメント