はじめに
程度の差こそあれ、「のめり込む」という現象は誰にでもあると思います。
・大好きな牛丼にハマって、毎日お昼ご飯は牛丼屋に行かずには居られない
・ハマっているアイドルがいる
・ゲームがやめられない
・ギャンブルがやめられない
・大好きな連続ドラマの続編が気になって毎晩遅くまで見てしまう
これらの現象を、「支配している」のか「支配されているのか」で整理をすると、支配をされている状態がこの記事で扱いたい状態です。つまり、自分の意思のコントロールが及ばないで、「そうせざるを得ない」という状態に陥っている状態に対して、僕自身の経験を通して、心の観点から考えたのがこの記事です。心を見つめ、その原因を理解し、心の持ち方を変えようとすることで解決の糸口としたい人に、この記事をお勧めします。
親からの支配
結論から書けば、依存的な性格は、親からの愛を今でも求めている心です。そして、それは幼少期にもらえなかったから、いつまでたっても求めるのです。人によっては80歳でも求めることがあると言われています。幼少期にもらえるはずの親からの無条件の愛は、どんな親でも等しく子どもに与えられるとは限りません。精神的に未成熟の親は、自分の気持ちを満たすことが優先されて、ありのままの子どもを愛するには至りません。親が満足できるように子どもを支配し、型にはめるのです。
僕の依存的な性格は、親に支配されている心から来ていると思いました。支配的な親を反抗期などは憎く思いながらも、支配されることが常態化すれば、逆に支配されるものがなくなれば不安に陥る。悪口を言いながらも、結局は依存している状態に、安堵さえ覚えたのです。寄りかかるもののある安心感。幼少期から寄りかかっていたものを、物心がついても評価する客観的な目を持たず、まるで幼児がお気に入りのタオルケットをずっと手放さないように、大事に抱え続けた。親との共依存とも言えるかもしれません。支配関係の親子関係に浸っているのです。
自分を抑圧して演じる子ども
では、「親の支配」とは何か? それは親の指示や命令です。「こうしなさい」とか「こうすべきだ」と言う親に従順な子どもは、心を親に預け、支配をされていると言えます。自己主張をせず、親の前で大人しく言うことを聞いている「いい子」です。「いい子」にも自分の意思はありました。ありましたが、無視しました。なぜか? 幼少期のことなので記憶にはありませんが、振り返って考えれば、自分の素直な気持ちや、自分の気持ちに素直な行動を取ったとき、親に抑圧をされたのだと思います。
もちろん、親は子どもを抑圧してやろうという悪意を持っていたわけではないと思います。子どもにそうさせるのが教育的だと判断したのだと思います。しかし、当の本人(僕)は、別のところに気持ちがあった。しかし、それを素直に口にすると、親はいい顔をしないはずだ、怒られるかもしれない。そう思うと、自分の素直な気持ちは無視して、親の言い分に従う。正確には従ったフリをする。演じる子どもになったのです。
それでも愛されたい
演じる台本は、親から与えられます。親の表情や機嫌が台本です。子どもであった僕は、その台本に忠実に演じました。もちろん、演じきれないこともあります。テストでいい成績を取る台本なのに、そうはできなかった場合、言い訳をする、少しでもよく見せようと平均点を偽る、嘘をつく、隠す。そうしながらも必死で台本通り演じようと頑張り、そのことにエネルギーを消耗し、いつも気力を奪われていたように思います。でも、そうしないと、親は不機嫌になり、不機嫌な親を見ることは、自分が拒否されているようで子どもの僕には恐怖でした。親の小言ほど不愉快なものはありませんでした。だから、完璧な演技を目指す。
そのためには、自分で感じたらいけないのです。自分がどう感じたかは問題ではなく、親がどう感じているかを察知する能力を磨く必要があった。だから、僕自身は五感を無視していたと思います。感情が消えたわけではありません。抑圧をしたのです。我慢していたのです。子どもですから、親に愛されたいと思う。でも、愛してくれる親はいない。愛してくれるとは、そのままの自分を受け入れてくれると言うことですが、親は自分の感情や機嫌を優先し、目の前の子どもの気持ちを受け取ってはくれません。愛情のバケツを満たしてくれないまま、一人で空っぽのバケツを抱えていた。依存的性格とは、このバケツを抱えて、ずっと親の方を向いている子どものことだと僕は思いました。自分がそうだったのです。
まだ欲しいけれど
僕が気づいたのは、そのバケツを満たしてくれる親は、もうどこにもいないと悟ったからです。それは、自分も親となり、わが子の心のバケツを満タンにしてやれたかと思った時に、自分は十分してやれなかったと後悔したことに起因します。そして、もはや社会に出ていこうとしている我が子に、何をしてやれるのか、と思った時に、もうバケツは子どもが抱えたまま遠くに行ってしまうのではないかと思ったのです。
つまり、子どもとしての僕は、親にまだ満たして欲しい。バケツは一杯ではありません。一方で親としての僕は、もう我が子のバケツを愛情で満たす具体的な手立てはないのではないかと焦っている。本来、ある程度の年齢になると、バケツは自分で満たしていくしかないと思いました。このことに気づかなければ、気づくまでずっと誰かがバケツを愛情で満たしてくれると思い込んでいるのです。誰かとは親であり、またはその代償としての依存できる対象です。それが牛丼でもタオルケットでも、ギャンブルでもゲームでもいいのです。そういう性質を持つ人は、何にだって支配されます。牛丼やギャンブルが悪いわけではなく、そこに依存してしまう自分の心に問題があり、その根っこは、親子関係で満たされなかった愛情のバケツであり、それを「誰かが満たしてくれる」と期待をしている自分の考え方がまずいのです。依存的性格とは、誰かが満たしてくれると思い込んで待っている甘えだと思いました。
支配から自由になる=自分を取り戻す
おそらく、幸せな幼少期を送った人には、この感覚はわからないと思います。自分の素直な気持ちをいつも全力で受け止めてくれた親のもとで伸び伸びと育った子どもは、なぜ自分の親に素直な気持ちが言えないのか、理解不能なはずです。しかし、言えない子どもは、厳しい上下関係で育てられ、抑圧が常態化し、自分の心を自分で押さえつけてきた子どもです。
依存しているものを、もうやめたい。例えば、ゲーム、アルコール、ギャンブル、過剰摂取してしまう特定の食べ物…。止めるためには、依存的な性質を自分が持っていることを知り、それがいまだに親への依存であり、親への愛の要求であることを感じてみてください。もしそうであるなら、その愛をくれるはずの親は、どこにもいないと認めることから、依存的性質を変えることは始まります。親としての自分が我が子に十二分にバケツを愛情で満たしてやれなかったように。それは親自身の精神的な未熟さに原因があります。同じ人間として、その不完全さを認めると、親を一方的に責めることでもないと思うでしょう。自分で抑圧していた気持ちを取り戻し、五感を生かして感じることを大切にすることが必要です。
おわりに
ここでは、幼少期に親から自分の感情を奪われ、自分軸を育むことよりも親の満足のために生きることに徹したために、親子で依存関係に陥り、依存心が生きる土台となってしまったことを、依存的性質の原因だと僕の経験から考察しました。依存していることで安心し、支配されているモノや行為を、止めるにやめられない。その根っこを幼少期の親子関係に見てとりました。そこから自由になるには、自分を取り戻すしかありません。自分軸が立ち上がらなかったから、支配関係に浸り、安堵さえ覚えていたのですから。自分を取り戻すとは、まず五感を生かして、自分の感じることを素直に言葉にしてみることからです。
なお、本文では、医学で言われている依存症とは区別するために「依存的性質」とここでは表現しました。


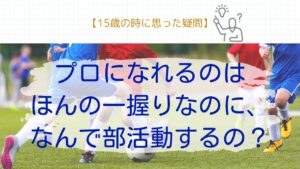

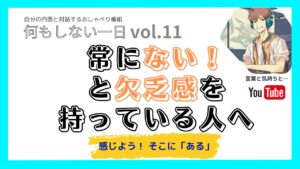
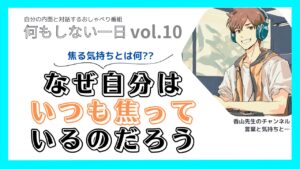
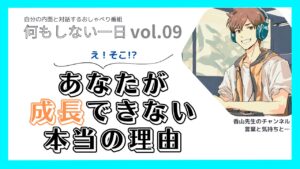
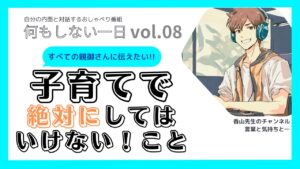
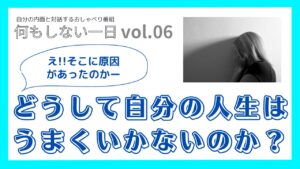
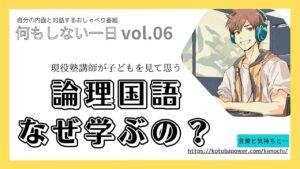
コメント