まず結論!
できるようになるには、できない事実を認めるところから。そこを素通りしてしまうと、当然ですが、できるようにはなりません。つまり、できない人は、素通りしている人です。できない自分とじっくり向き合えないのです。なぜか? 僕の場合は、怖さがありました。できなければ怒られる。だから、逃げたい。できるようになる努力をする前に、できる風を装い、できたことにしてしまおう。そして、できたことによって描ける未来を想像して、そこに逃げるのです。できない人は、できない事実と向き合えているかの自省からスタートです。現実には、逃げている場合が多いように思います。
「できない」は恐怖か?
誰でも、小さい頃に「できなかった経験」はあると思います。それは人間の成長にとって当たり前のことです。しかし、できなかった経験とその時に怒られた経験をセットで持ち合わせる人は、「できないこと=悪いこと」というふうに刷り込まれてしまいます。怒られるわけですから、そこには怒りの感情もくっついてきます。できなければ、自分はダメな子どもで、親に(または指導者などに)怒られるのだと思う。そして、怒りを持った指導者は、多くの場合冷静にできなかった原因を子どもにわかりやすく分析をして見せることもできないし、子どもの気持ちの確認さえしない。「できるようになりたいのか?」と確認をされ、子どもはそう思うなら学びに向かって気持ちが高まる。そうではない子どもは、できないダメな子というレッテルを自分で自分に貼り、次からできるようにするではなく、怒られないようにすることに意識が向いていく。「できない」を恐怖に変えるのは、愚かな親であり指導者です。できないは、ただの事実にすぎません。
「できない」事実が衰退と隆盛の分岐点
人は、できないところから成長が始まります。学習塾で子どもを見ていて思いますが、一通りの説明をしたのちに、演習をさせる。何をしているのかといえば、「できる」と「できない」を仕分けて、どこに課題があるかを見つけているのです。「できない」問題にこそ、その子の成長に必要なものが詰まっています。ですから「できない」を発見したのち、そこから逃げるのでは、成長はないのです。しかし、できなかった時に怒られた子どもは、恐怖を覚えているので、その状況から逃げてしまいたい。さらに、できるように冷静に指導者に導かれた経験が希薄なので、どのように克服していいものかもわからない。故に、できない事実を曖昧にしてしまう。そしてその恐怖から目を背けるために、できた風を装う。せっかくの成長の原点である「できないこと」を有耶無耶にやり過ごしてしまうのです。
認めない先には悲劇が待っている
できないことと真っ直ぐに向き合えない子どもは、どのようになるのでしょうか。そのことができないということは、大きなことではありません。それと向き合えない精神性が、その子の未来に大きな影を落とします。まず、できた風に装い、できる自分を演じる、つまり自分自身に嘘をついた状態が普通になります。偽りの自分を生きることになります。当然、本人は苦しいはず。しかし、できないと言えない。怒られると思うからです。できないことをできない、わからないことをわからないと言えないと、成長はない。わからないことを、わかった顔をして生きていくと、そのうち、自分はなんでもできると錯覚をします。できないと認めることは恐怖だからです。なんでもできると錯覚をすると、その子の未来は、地に足のつかない虚飾に染まっていきます。見栄を張る、妄想に生きる、嘘をつく(一発逆転の発想もこの辺りに根っこがありそうです)、権力を過剰に欲しがる…ロクな未来はありません。子どもの頃に、できなかった事実に怒りの感情を添えられることが常態化していた子どもの未来は、どこまでも落ちていきます。
成長をしたいなら
成長とは、自分で自分の価値を認められて、その価値を自分で高めていけることです。精神的な成熟といってもいいと思います。その初めは、まず自分ができないことを「事実」として認めること。そこからは自分の気持ち。それができるようになりたいのか? 本当に自分のやりたいことなのか? 自分の気持ちに正直になるしかありません。そこに、趣味が有効だと僕は思いました。
僕は、プロになれる確率が極めて低いスポーツを、なぜ一生懸命にやるのだろう?と疑問に思っていました。あるとき出した答えは、「好きだから」。好きだからやるのです。好きなことに打ち込める時間に充足感を覚えるから、やっているのです。このことは、自分の気持ちを知る上で、つまり生きていく上でとても大切な時間だと思います。そして、そこで小さな感動体験を重ねること。できないことができた、でもいいと思います。野球ならキャッチボールが1回でも綺麗にできた。思い描いたフォームで投げられた。相手の胸の前にボールが吸い込まれていった。そのような手応えが小さな感動体験です。
趣味を否定し、できないことをできないと認められなかった子どもの頃の自分に言うなら、感動体験を求めて、いろんな世界を見たり飛び込んだりしてごらん、と言いたい。最初は趣味の世界です。自分が好きな世界のことなら、心から人に伝えようと思うし、自分の言葉で語ろうとするかもしれない。そのことが、できないことをできると錯覚したままの自分の狭い世界から抜け出す可能性になったかもしれない。自分で工夫をするということが高い確率で起こり得るのが趣味の世界だからです。それは、自分の失敗を立ち止まって、自分で冷静に分析することにつながります。どの分野でも、前に進むにはそういう失敗を乗り越える時があり、現実を認め、分析する思考が働きます。成長ができずに悩んでいる人は、いったんそのことから離れて、趣味の世界で自分の好きなことを追求する経験を持てと言いたい。それは無駄ではありません。プロにならないならなぜ野球をするのか、という当時の自分の疑問に、このような考え方をぶつけることで、のめり込める世界を持たせてやりたいと僕自身が思います。そこから子どもなりに学べるものがあります。趣味をバカにすること勿れ、です。
まとめ
✅ なぜ同じ失敗の繰り返しから抜け出せずに成長できないのだろうと思っている人はできないという「事実」に「怒られるという恐怖の感情」がくっついていないか振り返る。
✅ できないは、ただの「事実」。
✅ できないことや失敗したことは、成長の原点。
✅ そこから自分はどうしたいのか、自分の気持ちを確認。
✅ できるようになりたいと渇望するなら、その方法を知る、指導者に聞く。
✅ このような過程を自分のものにするために、自分の好きなこと(趣味など)に没頭することも有効。
✅ 事実から目を背けて、できる自分を演じても、自己の成長には繋がらない、同じ失敗に止まりながら、失敗を失敗ではないと装う人生しかない。
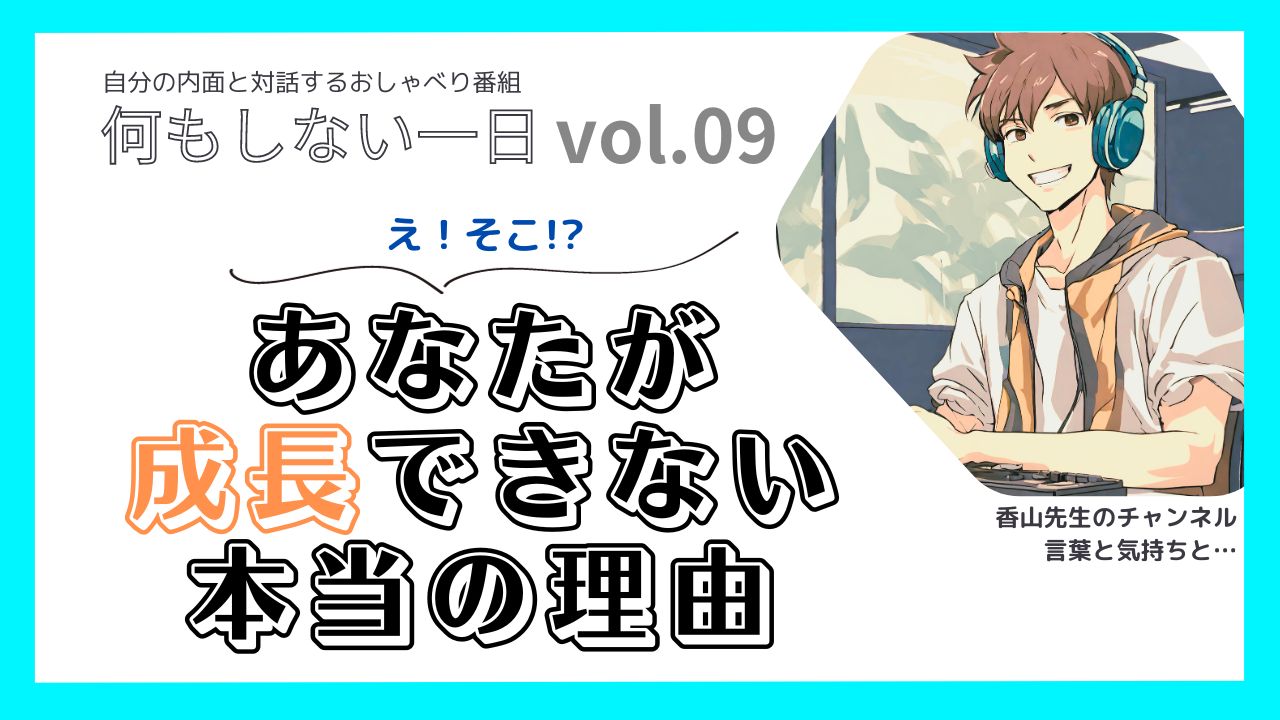

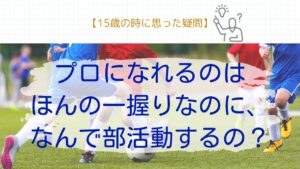

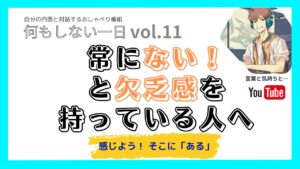
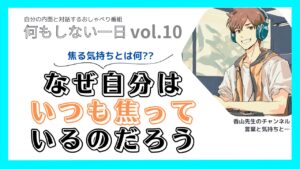
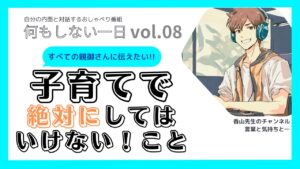
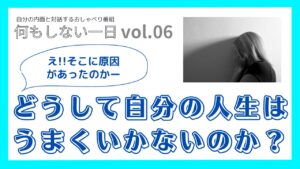
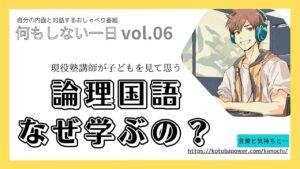

コメント