はじめに
この記事は、なんだかイライラすると感じる全ての人に向けて書いています。大人、子ども問いません。おそらく、何かの外的要因があってイライラしているのだと思います。結論を先に書けば、それはどんなことであっても、自分の感情と思考が引き寄せたものです。普通に暮らしていてイライラするのは、その感情と思考を変えた方がいいよというサインだと考えてみませんか。そこに、対処療法ではない本質的な解決策があります。

その感情は自分が理由だと引き受ける
イライラしている人を見かけることがあります。コンビニのレジ待ちの列にも、銀行の窓口の順番待ちの中にも見たことがあります。虫のいどころが悪いのか、恋人と別れ話を拗らせているのか、親子関係にうまくいかないことがあるのか…。全部、相手が絡んでいます。コンビニのレジ担当者、銀行の窓口の人、恋人、親と子。イライラの原因は相手だと思い込んでいるうちは、あなたのイライラは無くなりません。これは、僕の経験上、そう思います。人間関係だから、相手と自分は五分五分だと思うかもしれません。しかし、そこを、自分が主体となってその感情を引き受けてしまえるか、そこに大きな人間的な成長があるのではないかと考えます。

相反する欲求がぶつかるとき
イライラするという感情は、どういうものでしょうか。何かを我慢しているのではないでしょうか。順番待ちにイライラする人は、次の予定の時間を気にしているのかもしれません。今日は、銀行に行くだけで、あとは帰って寝るだけだという人は、そんなにイライラしないかもしれません。順番待ちの際のイライラが、空腹が理由ということがあるかもしれません。食べたいのを我慢してる。次の予定に向かいたいのを自分の意思とは無関係に我慢している場合は、「遅れます」「ちょっと銀行が混んでて、そちらに向かうのが遅くなるよ」と言えれば、イライラはおさまるかもしれません。恋人と別れ話をしている場合はどうでしょう。我慢せずに本心が伝えられたなら、とりあえずはイライラしないかもしれません。本心に対して我慢を強いられている。もっと恋人に甘えたいのに、それが叶わない時、気持ちがトゲトゲしてきます。
原因を探ってみよう
イライラの事情はさまざまですから、いま書いたことはほんの一例に過ぎません。大事なことは、このようにその原因を探ってみることです。なんで順番待ちにイライラするのか? 仕事の合間に職場を抜けてきているので、早く職場に戻りたいというのがその原因だとしましょう。しかし、イライラしても状況は変わりません。順番は、前の人から一人ずつやってくるだけです。同じ状況に、イライラしない人もいます。黙って平然と待てる人。慌ててもどうにかなるものではないとわかっている人は、心の奥底でわかっているのです。待てる人は、どんな人でしょうか? それは私が思うのは、幼い頃に、親が待ってくれた人です。
待てない親が、待てない子を育てる
早くしなさい! いつまで食べてるの! 早く学校に行きなさい! 早く勉強しなさい! いつまでかかってるの!
そういうふうに言われてきた子どもは、常に心が落ち着かず、待つことに不安が伴うのだと思います。すぐに結果が来ないと不安になる。不安からイライラは生じているように思います。

言葉の観点から言うと、待てない親に育てられた子どもは、感情的になることが多いのではないでしょうか。不安が感情に結びつき、そこに思考の入る余裕はありません。待つということは、考えることでもあります。親の立場で考えてみましょう。子どもが算数の宿題で、九九のプリントをやっているとします。しかし、苦手で鉛筆が進まない。集中力も切れて、意識が散漫になっています。「いつまでかかってるの!」九九のできる大人は、子どもを感情的に怒鳴るとします。子どもからすれば、恐怖でしかありません。できなければ、怒られる。待てる親は、筋道を立てて子どもに話ができる親です。「どこがわからなくて鉛筆が止まってるの?」と冷静に問える親です。
そのままの子どもの状態を愛する
待つというのは、愛です。
子どものお話を、終わるまで待ってあげる。
子どもが遊んでいるのを、飽きるまで待ってあげる。
泣いている子どもが、泣き止むまで待ってあげる。
どれも、とても大事なことだと思います。
待てない人は、幼少期に親に辛抱強く待ってもらったことのない人かもしれません。
つまり、愛が十分ではなかったのかもしれません。
こんなことを言うと、うちの親を否定するのか、と言う向きもあると思います。否定ではなく、事実を知ることが大切なのです。親も人間です。自分も含めて、完璧な人がいないように、親だって完璧ではないかもしれません。忙しかったのかもしれないし、親自身も幼少期に急かされながら育ったのかもしれません。自分は親に待ってもらえなかったのだと知ることが、この問題を解決する第一歩です。
イライラは自分の心が決める
イライラする気持ちは、何かを自分の中で抑圧をしてきた結果だと自分を振り返ってみる。相手が全て悪いわけではないと思ってみる。自分の心の中に何か不安に思っていることはないかと疑ってみる。その不安は、待てない親に育てられた幼少期に根っこがあるのではないかと考えてみる。このことを意識するだけで、随分と自分の心が成長できそうに思います。
その人の欠点は、自分にもある!
同じ事象に遭遇しても、イライラする人と、しない人がいます。レジが遅いというケースなら、レジ担当者の手際の悪さが原因か? もしその人が新人であれば、何事にも初めてはあるよなあと思えるか。自分の子どもがレジをやってたら…、自分の母親がレジをやっていたら?と考えることもできます。「自分なら」とも考えられます。自分がレジをやっていて、初めてで手際が悪く、イライラしているお客さまの罵声を浴びたら・・・などと考えることもできます。そうすると、「なんだ! 自分がイライラしていたことは、自分が引き起こすこともあり得ることだ!」と気づくはずです。
言葉の力
視点を変えて考えてみる。相手の立場に立って考えてみる。このことで、随分と気持ちは楽になるものです。視点を変えるとは、主語を変えることです。「あいつが悪い!」ではなく「自分が悪い!」「自分の考えが幼い」というふうに。主語を変えると視点が変わり、視点が変われば考えが変わり、考えが変わると気持ちが変わります。レジ待ちの間にも瞬間で気持ちを変えることができるのです。人に対するイライラは、実は自分の考え方の問題だと気づけば、随分と生きやすくもなろうと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。これからの寒い季節、暖かい飲み物を飲んで、ゆっくりとした気持ちでお過ごしください♪
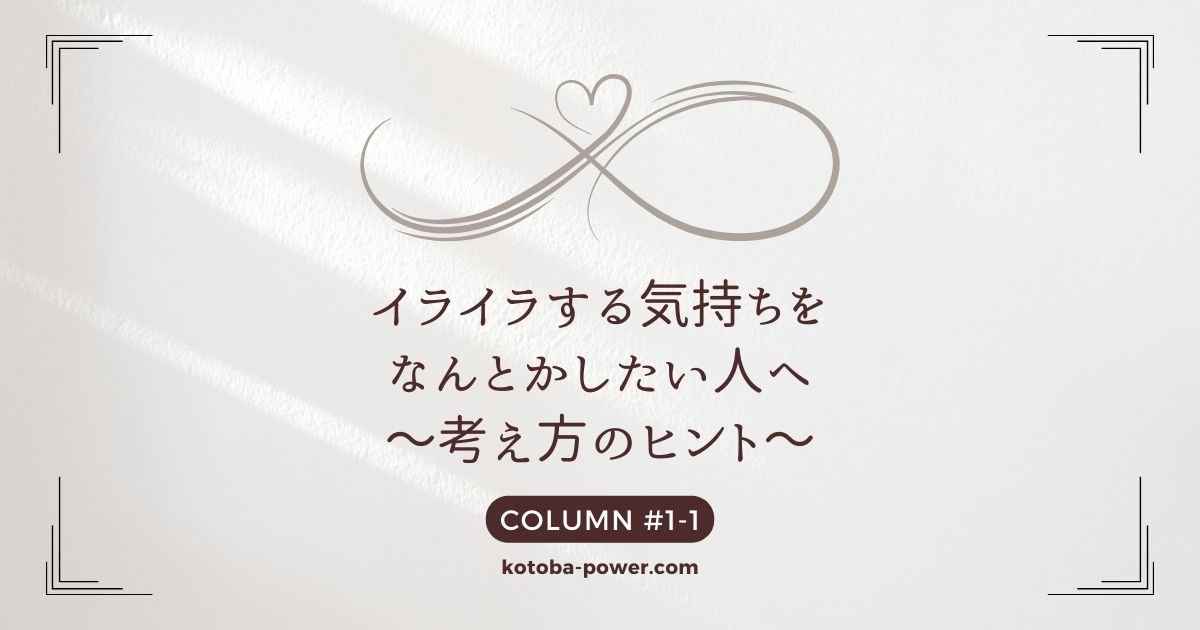
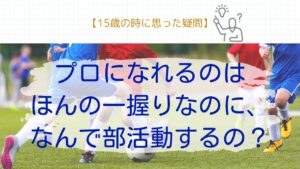

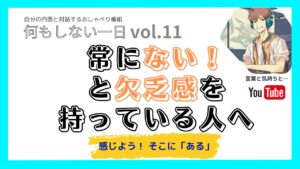
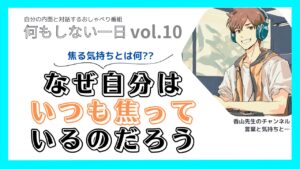
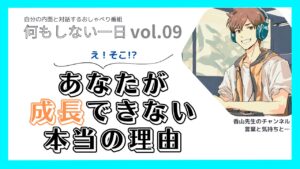
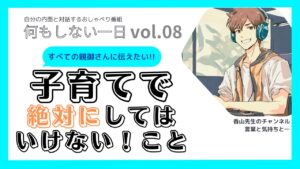
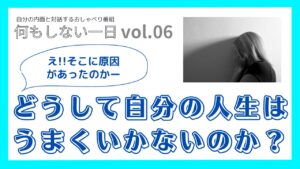
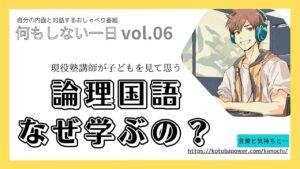
コメント