まず結論!
子どもの「できた」「できない」で、できなかった時に、怒りをぶつける。これはご法度です。できなかったことは、ただの事実。その事実に怒りをぶつけると、子どもは「できなかったら怒られる」という恐怖の感情をセットにします。恐怖はできるだけ味わいたくないので、できないことを事実として認めない子どもになります。できたふりをする。装う、演じるようになります。そうすると、その子どもは地に足をつけた成長ができず、ふわふわとした根無草のような上っ面の体裁を整える子どもになります。そして何より、子ども自身の精神が成長しません。大人になっても、自分で自分を高めることができない人間になります。
「子どものためを思って」!?
できない子どもを「叱る」を超えて「怒る」というのは、昭和の時代からスポーツの世界では散見された出来事だと思います。それによって、その競技が嫌いになってやめたという投稿を数日前もSNSで目にしました(2023年にこの記事を書いています)。その投稿には、怒った指導者に対する恨みのようなものが書かれていました。その怒りにより、自分は好きだったそのスポーツが嫌いになったとありました(投稿者は指導者が嫌いとスポーツが嫌いを重ねてしまっていますが…)。指導者は、怒ることでプレイの改善が為されて強くなれる、と思ってのことでしょうが、怒られた方は、とりわけ一生懸命やっていたり、そのポイントで外してはいけないと思ったりして頑張っている子ども。そういう子どもにとって、その怒りは意味のないただの感情の爆発としか取れないように思います。これは、僕自身の経験から想像のつくことです。
スポーツでも学習でも
スポーツだけではなく、学習の面でも同じことが言えると思います。親子で勉強を見ていると、つい感情的になって手が出てしまうという話を、これも数年前に聞いたことがあります。令和の時代に、昭和の親がやったという話です。もちろん、そう話してくれるということは、後悔もされているのだと思いました。これは珍しいケースではなく、複数の親御さんからそのように聞いたことがあるので、そういう家庭は一定数あったのではないかと思います。僕自身も経験があります。怒りをぶつけられた経験もあるし、自分自身も親としてやってしまった経験もあります。その時の子どもの反応は、火を見るよりも明らかです。怒られると、萎縮し、理由もわからないから混乱し、混沌の中で小さくなって固まることしかできません。何が間違えた原因か、丁寧に大人が理由を教えながら導く以外、抜け出す方法はありません。そして、それができるのは指導者、つまり大人の側です。できる人が、できない人の上に立って偉そうにしているのです。おかしいですよね。

それは、ただの「事実」
できなかった。これは一つの事実です。そこに「良い」も「悪い」もないのです。おそらく、スポーツであれば順位がつく、学習であれば点数や成績がつくことで、「できないことが順位化されてしまう」ことに、優劣意識の激しい指導者は勝ちを取ろうとして、「できないこと=悪」と思ってしまうのだと思いますが、子どもの成長からすればその意識は邪魔でしかありません。できなかった事実を認め、「できるようになりたいのか?」という子どもの意志を確認をして、そうであるならそのために何をどうすればいいか道筋を示すのが指導者の役割です。
できずに怒られた子の末路
できなかった時に指導者から怒りをぶつけられた子どもは、先にも書いたように「できなかったことが悪いこと」という関係が刷り込まれます。悪いことは、隠したいことです。しかも、人は誰でも意味もなく怒られたくない。そのような気持ちが「できたふりをする」「自分はできている風を装う」ようになります。その瞬間、例えばスポーツのプレイのミスとか、試験問題の間違いなどは、確かにできていない。しかし、「自分はできるんだ、次はできるんだ」というような思考が働くのです。できないわけではないから、次はもっと難しいところを目指そうとするのです。決して「自分は『いま』『この目の前の課題が』できないから理由をはっきりさせて乗り越えたい」とは思えない。怒りの感情からいち早く逃れたいのです。未来に逃げる。だから、現実的な成長がない。ただ逃げて、できる自分を演じることに長けていきます。プライドばかりが高くなり、現実を生きる手立てを失います。
精神の成長がないまま大人になると…
できないことを発見して、それを一つひとつ乗り越える経験が子どもの頃にできると、その子は、人の成長にはそのような過程を経るのが普通だと思います。しかし、できないことが発見されても、そこに怒りの感情がくっつくと、怒られないようにそれを隠し、認めず、できた風を装う。自分の課題と向き合うことを避けていますから、子どもの成長はありません。子どものまま大きくなってしまいます。勉強は大きくなってもできるんだと言われますが、その前提は、できないことや知らないことを自分で認めることが最初です。なんでも知っていると思うのは、うわっつらしか見ていないし、見ようとしない底の浅い人間です。
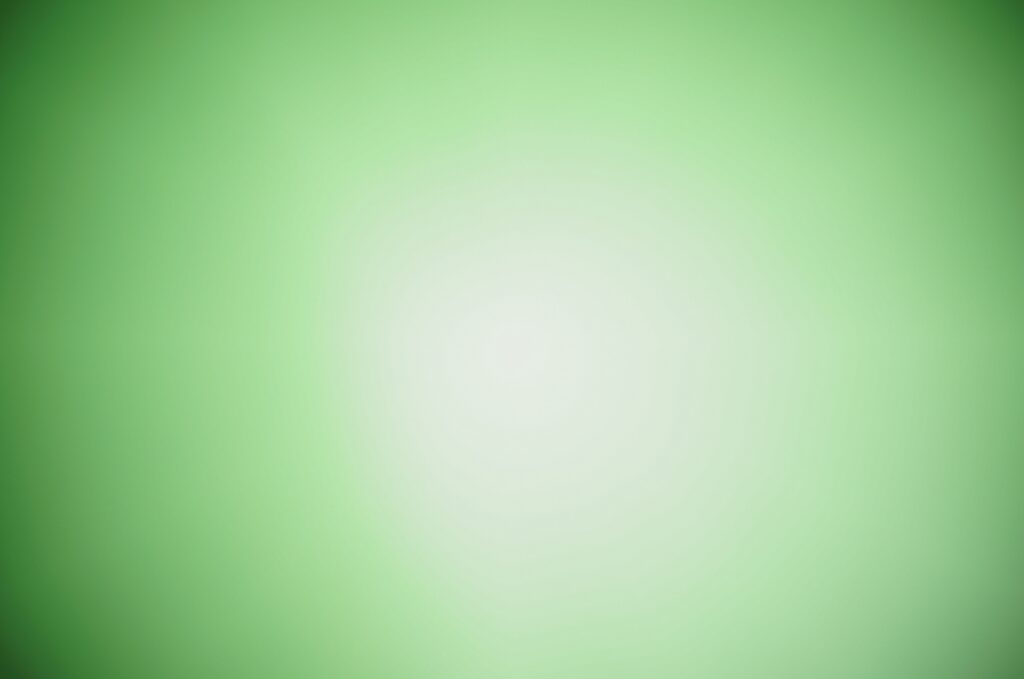
怒りは成長の邪魔になっている
知らないことを知ってみたい、自分はわかっていないのだ。素直にそういう気持ちになれるのは、小さい頃にできなかったことをできないと自分で冷静に受け止められた子ども。それは、指導者(親も含む)ができなかった時に怒らなかったからです。何が理由でできないのか、冷静に捉え、導けたからです。怒りは、成長の邪魔になっています。できると期待した指導者は、できない子どもに向き合う時、それは何が理由で怒るのでしょうか? おそらく指導者として優れていることを誇示したい気持ちがどこかに潜んでいたのではないでしょうか。子どもを道具に何をしたいのですか?と言いたい。その奢った気持ちが、子どもの心の成長を潰しています。
事実として受け止めることから
すでに怒っている指導者は、今からでも遅くありません。
✅ 子どもができない事実を、事実として受け止める。
✅ できなかった子どもに、できるようになりたいのか、意志を確認する。
✅ できるようになりたい!と渇望するなら、そのための道筋を示す。
これが指導者です。この過程に、怒りの感情はどこにもありません。あるなら、それは指導者自身のエゴにすぎません。
みんなで高みをめざそう
指導者の暴力が常態化して、厳しいほど強くなれると信じられていた時代は終わりました。僕は、それはとてもいいことだと思います。二元論の限界、つまり強いか弱いか、という価値意識の中で競争する時代も、やがて選択肢の一つとしては残ると思いますが、それが全てという見方もなくなっていくように思います。
競技スポーツは勝つことに意味がある。正しくは、勝ちたいと子どもが願うなら、そこを目指して子どもの実態に寄り添いながら、子どもの精神の成長をめざす過程に意味がある。その精神の高まりの結果、勝つこともあれば負けることもある。それだけのことではないでしょうか。子どもの精神の成長を置き去りにした勝ちは、あんこの入っていないどら焼きのようなものです。見栄えはどら焼きでも、中は空洞。被害者は子どもです。この記事をお読みいただいた皆さんと一緒に、僕自身も意識を改め、謙虚に知らないことを知らない、できないことをできないと認め、そこから学びに向かいたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございます!
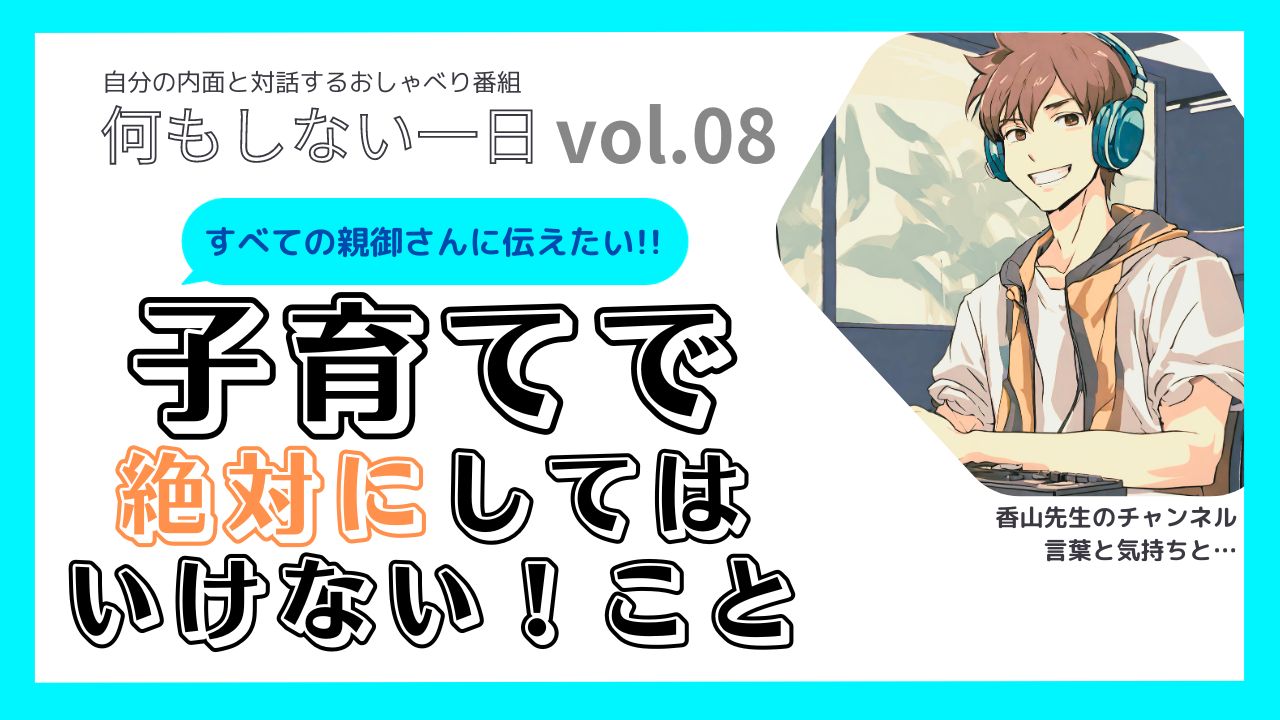
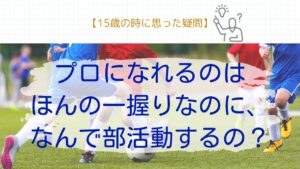

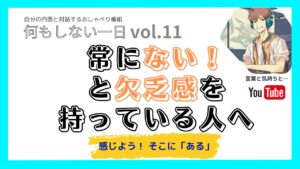
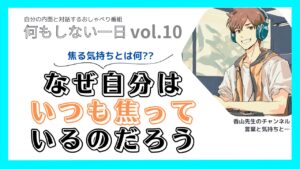
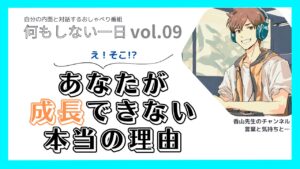
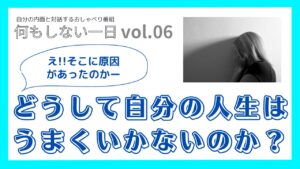
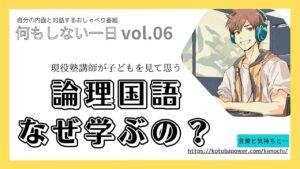

コメント