はじめに
高校に始まって、小学校の国語の授業でも「論理」ということが重んじられようとしています。僕は、論理的に読む、書くということを主宰する国語の単科塾で教えて8年になります。それと二足の草鞋を履くように約20年ほどコピーライターとして数多の人に話をお聞きしながら、その人の気持ちの言語化が大切なことを直観しました。テストの点数のための言葉ではなく、「生きてくための言葉」という視点で塾でも子どもと向き合っています。そのような立場から、論理国語を学ぶ意味を考えてみたいと思います。
前提として
国語を学ぶ上で、私たちが感覚としてでもいいので大切にしたいことがあります。それは、言葉への信頼感です。それがなければ、論理国語は成立し難いものとなってしまいます。言葉の力を盲信しろということではありませんが、前提として持っておいた方が学びに向かいやすいと思います。
・言葉によって自分の心を成長させたり、変えたりすることができる。
・言葉によって、人との関係性を豊かにすることができる。
・言葉によって、社会をより良くしていくことができる。
論理国語の領域
万能ということはありませんが、教えていく中で、概ね以下のような領域で学びが深まっていくような手応えを持っています。
それは、論理的思考、豊かな情緒、語彙(概念の獲得)の3つです。
・論理的思考とは、主観を排して、客観的に書かれている文章を読み取る力であり、逆に自分が人に何かを伝える時に、主観的にならず、筋道を立てて表現できる力となるものです。
・豊かな情緒とは、読み取った内容を踏まえ、自己の経験などと対照し、自分の生き方やあり方などに結びつけ、精神的な成熟を目指す時に大切なものです。また、人との関わりの中で生きていく(課題を見出し、解決を図ろうとする)中では、心と心の結びつきが大切。心とは気持ちのありようであり、その気持ちが言葉として交わされます。また、自分の気持ちと深く向き合うことで、人を理解することにもつながります。上の「論理」とは、他者意識から渇望するものです。
・語彙とは、具体的な物を指す言葉(訓読みの単漢字)を超えて、次第に抽象的な概念(音読みと音読みの合わさった熟語など)となります。人は持ち合わせていない概念を使って思考することはできません。所有する語彙の範囲でしかものを考えることができません。論理の力を働かせて読み取った文章内容を概念として整理し、思考を深め、広げる時に、語彙は武器となります。
学ぶ目的(めざす子どもの姿)
・第一に、筆者の書いた文章を正しく、正しくとはありのまま、つまり主観を入れずに読み取る姿には、自己主張するのではなく、文章と謙虚に向き合おうとする心があります。人の言うことを黙って最後まで静かに聞こうとする、尊い姿です。(親になった時に、子どもと向き合うとても大切な姿勢だと思います)
・第二に、読んだ内容を踏まえて、自分で概念を磨く子ども。つまり、読んだ内容を自分の経験と照らしたり、自分なりに意味づけたり価値づけることを通して、先程までの自分の考えに固執せずに、自己の世界を広げたり、深めたりできる子ども。
・第三に、教材を離れても、自己の価値観を自らの学び(経験や学習など)によって更新できる子ども。固執とは、思考停止であり、正しさや「べき論」に陥る、排他性や甘えにつながりやすいものです。豊かな生き方につながりにくいものです。精神的な成熟を目指しながら豊かに生きたいと願い、論理国語を生かしながら豊かな言語を使って人生を楽しむ子ども。
なお、これらの姿は、例えば高校卒業時に完成するものではなく、その学齢に応じた一連の思考と感情の働きが見られ、スパイラル方式で成長するものです。
以上のような点で、論理国語は、学校のテストのためを超えて「生きてく」上でとても意味のある学びだと考えています。

論理国語はあくまで学校の教育内容の一つですが、大人向けにプログラムを独自に考えています。ご興味のある方はお問い合わせください。(このサイトのプライバシーポリシーと免責事項のページの最下部に「お問い合わせフォーム」があります)
美味しいコーヒーを飲みながら、論理について思いを馳せてみませんか…



この内容をyou tubeで視聴もできます!「言葉と気持ちと…『香山先生』」ぜひチャンネル登録もお願いいたします!! ありがとうございます。
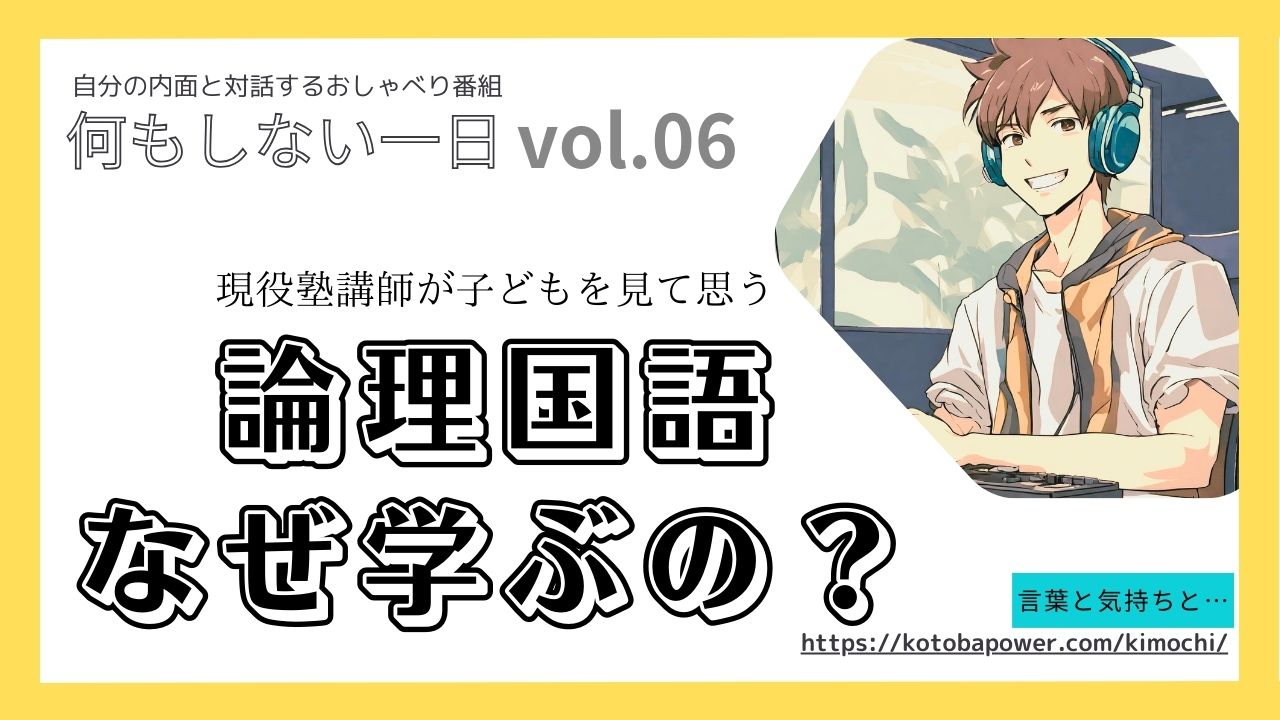
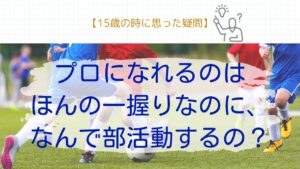

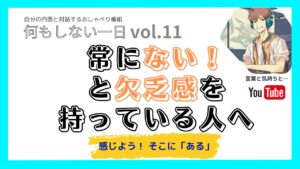
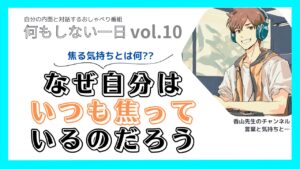
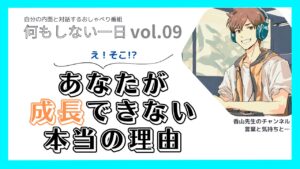
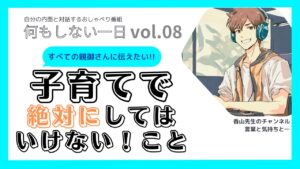
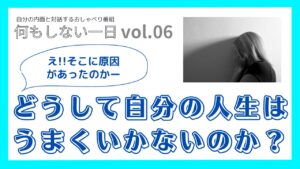

コメント