はじめに
「べき論」とは、「こうすべきだ!」という強い意志や信念に基づいて語られることが多いものです。それは生活習慣から作業工程、生き方に至るまで、さまざまなシーンで見ることができます。ここでは、生命の安全に関わるものは除外してお話をします。生命の安全に関わるとは、例えば次のようなことです。ある自動車修理工場でエンジンをバラしていたエンジニアが、部品を一つずつ、バラした順番に見事に並べていました。なぜ、これほどまでに綺麗に並べるのかと問うと、車は人の命を乗せている。その車のエンジンを修理して元通りにするとき、一つでも部品が欠けた状態で組み上がることのないように、バラした順番に並べるのだと言うのです。それは熟練工の作業手順で「そうすべき」なことです。しかし、こういうこと以外に「べき論」を振りかざす人とは、どういう人でしょうか?
それは盲目の信仰に近い
こうすべきだという主張に溺れる人は、思考停止しているのではないかと思うのです。無条件に信じたり崇めたりする行為と大差のないことです。自分はどう思い、どう感じるのか? そこを大切にすれば、「こうすべきだ」という考え方はおかしいと思うかもしれません。それでも疑問にも思わないのは、あなたの気持ちが抑圧をされていると考えてみることはどうでしょうか?

親に感情を奪われた子ども
何に抑圧をされているのか? 多くの場合、それは幼少期の親に原点を見ることができます。親から「こうしなさい」「こうしないといけない!」と頭ごなしに育てられると、それを守ることが絶対だと思い込んでしまいます。幼少期の親の命令は、その子にとってみると、絶対です。衣食住を満たしてくれるのがその親しかいない場合、それは自然なことです。つまり、親が子どもの気持ちを聞いてあげようという姿勢のない場合、子どもは常に親の命令や要求に忠実であろうとします。
普通は、子どもが親に要求する
本来は、子どもが親に要求をするのが自然です。おむつが濡れて気持ち悪い場合、幼児は泣いてその不快を表現し、親に替えて欲しいと要求をします。至って自然なことです。そこで、おむつを取り替える行為を例にすると、「よく教えてくれたねー、ありがとう」とニコニコして子どもと接し、取り替えたら「さっぱりしたね」と笑顔でスキンシップをはかる親があれば、一方で、イライラしながら取り替え、そのまま放置する親もいると思います。忙しいとそうなる気持ちもわかります。しかし、赤ちゃんはその様子を感じ取る。自分の要求を伝えたら気持ちよく受け入れてくれる親か、不快な感情をぶつけられる親か。まだ言葉では表現できませんが、感覚として受け取るのではないでしょうか。愛情を受け取るか、不機嫌と抑圧を受け取るかの違いです。後者の親は、子どもに要求するタイプの親です。静かにしておいてくれ、泣くな、騒ぐな、あっちに行っておけ…。親が子どもに要求をしているのです。子どもは、満たされない気持ちを抱えながら、黙って辛抱するしかありません。
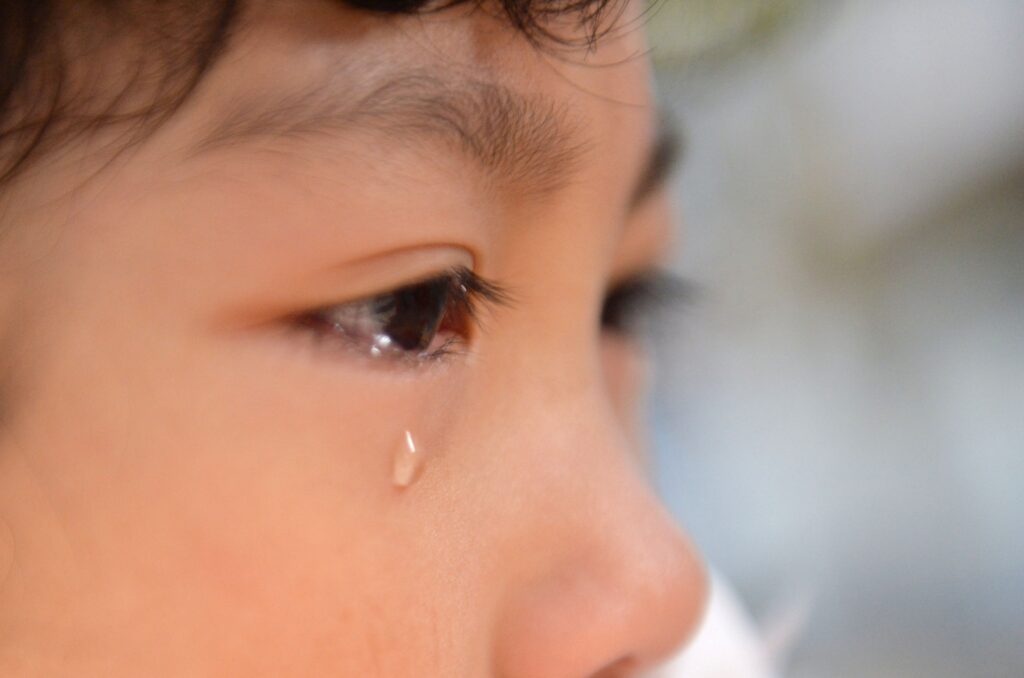
なぜ親は子どもに要求するのか
子どもはわがままなものです。要求し、欲望をぶつけ、それを親が受容しながら愛を知り、気持ちを満たしていきます。それが逆転すると、子どもは我慢するしかありません。要求が満たされないことで泣きわめくこともあると思いますが、泣き疲れたら、あとはひたすら我慢し、自分を責めることさえあるように思います。自分自身、そこの記憶はありませんが、僕の場合は、自分の気持ちを閉じて、親の要求や顔色に敏感な子どもだったと思います。だから、聞き分けのいい「いい子」と親は勘違いしていました。勘違いされても、そう思われたなら、なおさら自分もいい子を演じようと熱を上げます。いい子にしていたら、親は機嫌がいいからです。渇望している愛がもらえそうに思うからです。
「心のおむつを脱げない親」
そういう親は、心が未成熟な親です。言ってみれば、幼児の精神性のまま、年だけとったのです。心はおむつをしている幼児の年齢と変わりません。「心のおむつを脱げない親」とでも言いましょうか。親の方が、子どもにたくさん要求したいのです。ああしろ、こうしろ。なぜか? 自分にとってその方が都合がいいからです。子どもの気持ちが大事だとは微塵も思っていません。子どもがやりたいように伸び伸びとさせることを押さえ込み、お行儀がよく、大人しく、従順な子どもにしておきたい。ここに「こうすべきだ」という「べき論」が登場します。
「べき論」って何?
子どもは自由でわがままな存在ですから、自分の気持ちをある程度、または完全に閉ざして、親の主張する「べき論」に従うのです。しかし、それにどのくらいの意味があるのでしょうか? そうしなければ、どうなると言うのでしょうか? 例えば、学校の勉強を例にとりましょう。それは違うだろう、学校教育は一律にやるべきだと主張される方もいると思います。しかし、子どもの気持ちのないところに、学習もありません。勉強以外に興味関心がある子なら、どうしますか? いま、周りの友達と同じように学習をしなければ、どんなリスクがあるのか? 遅れをとってしまう、がその主なリスクでしょう。そのリスクを親子で背負う覚悟があれば、いましなくてもいいのです。子どもがやりたいことを満足するまでさせる方が、長い目でみれば成長につながると思います。「べき論」は責任を取りたくない親の隠れ蓑だと言えます。
子どもの気持ちに優先する「べき論」はないのでは?
実際に、自分の気持ちに忠実に生きている人がいます。逆に「べき論」に縛られて生きている人もいます。それぞれに満足ならいいと思いますが、ここで話題にしたいのは、子どもの気持ちに優先する「べき論」はほぼないということです。目の前の子どもの様子をよく観察して、子どもの生き方、あり方を一緒に考えていくことが大切だと思います。なぜなら、子どもの気持ちを受け止めてやれる1番の存在は親だからです。親にそのままの自分を受け入れられたい、というのが子どもです。受け止めきれないのは、そうした場合に発生するかもしれない責任を、親が引き受ける覚悟がないからです。

自分の気持ちと対話を始めよう
幼少期に自分の気持ちを閉ざし、親の主張する「べき論」に生きた人は、自分を振り返っても、演じている場合が多いと思います。本当の自分ではない自分を、自分だと信じて生きている。だから、人生の選択を誤ることが多い。進学、就職、結婚などは大きな選択の例だと思います。気づいた時に、リスクを引き受けながらやり直しをして、より良い方向に舵を切ることは、生き方の改善策と言えます。
幼少期からみれば、そのくらい「べき論」を生きることは、人生に大きな影響を与えることになります。もちろん最期まで「べき論」を生き抜く人もいると思います。気づかず、不満に思わない人です。それが幸せかどうかは、その人によると思います。しかし、まだ未来のある子どもを育てる親にとって、また少しでも気づいた人は年齢によらず、自分の気持ちと対話することを始めることが、精神の成熟につながると思うし、「心のおむつを脱げない親」にならない方策だと思います。子どもの感情を奪い取る親は、親子ともに不幸な未来しかないということです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。デロンギのコーヒーメーカーで、柔らかで芳醇なコクのあるコーヒーをお楽しみください。心が柔らかくなって、少し「べき論」から自由になれそうに思います♪
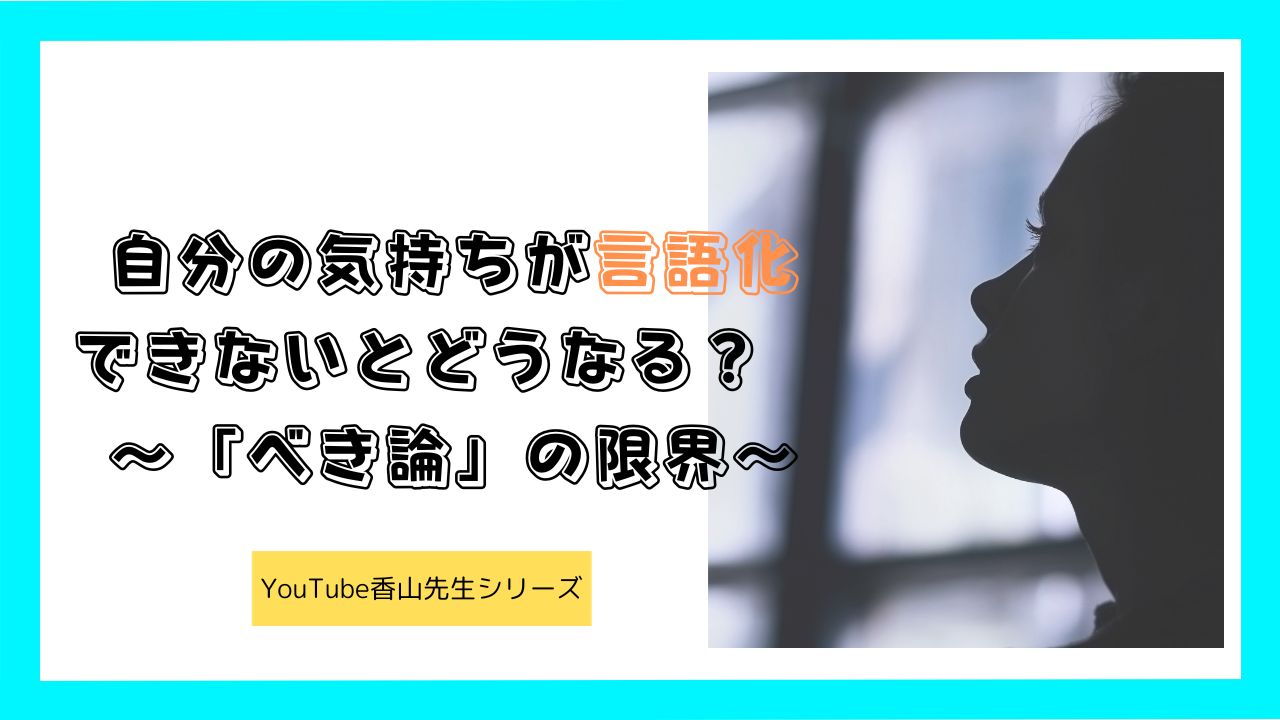
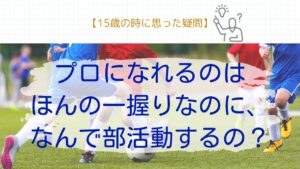

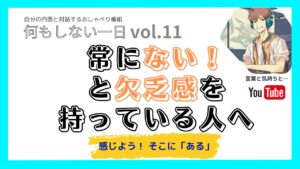
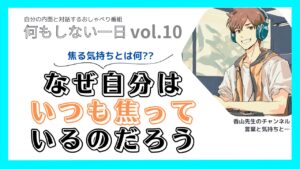
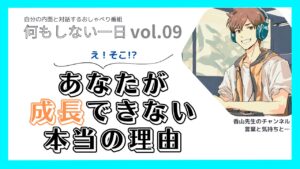
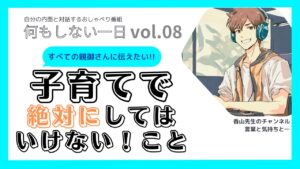
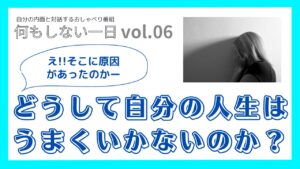
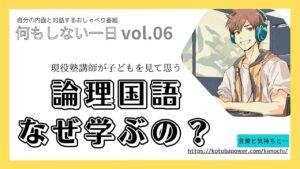
コメント