はじめに(問題意識)
僕が主宰している学習塾の生徒を見ていて、思うこと。同じことを教えても、成果が違う。成果の違いは、そもそもの学力差だと見る人もいますが、それを埋めようと子どもは頑張っています。また、そういう意思のある生徒が塾に来ています。では、彼らの違いは何か? 私が感じるのは、取り組みの姿勢の違いです。もちろん、みんな黙々と真面目にやっています。それでも差はつく。そこに、取り組みの姿勢の違いを見て取ります。それは具体的には、集中力とか意識の向け方といったようなことだと感じています。
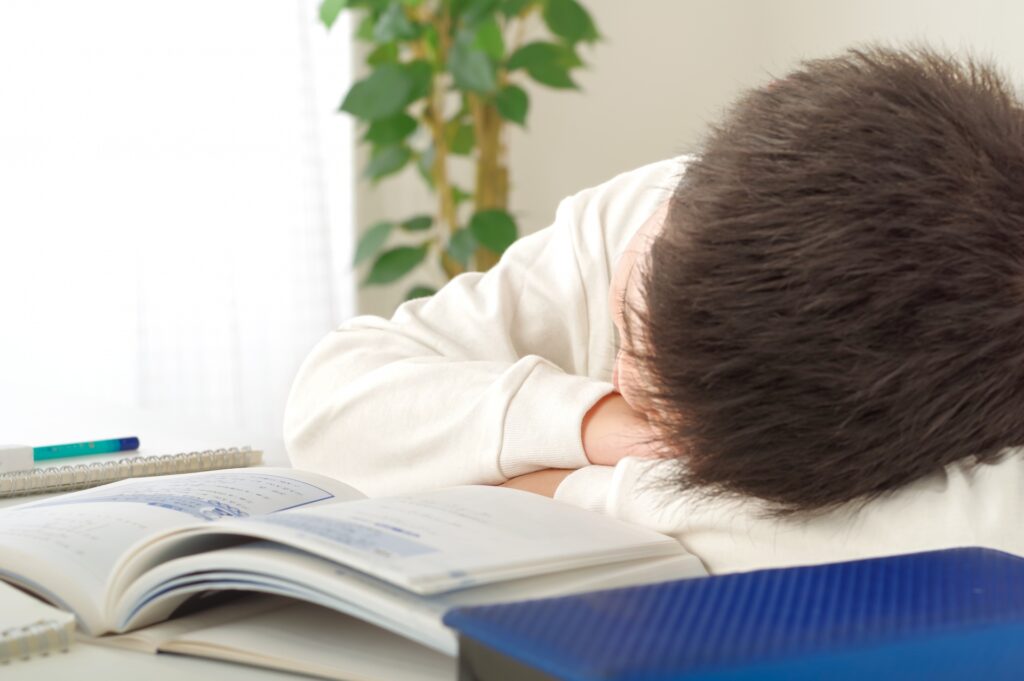
いまやっていることに、どれだけエネルギーを注げるかです。集中力と言ったりもします。しかし、集中をしないといけないことは、みんなわかっています。でも、できない。意識がすぐに途切れる。散漫になる。頭に別のことが過ぎる。他ごとが始まり、その時間を経て、また学習を始める。また他ごとが始まる。こういう状況が繰り返されるのが、成果の上がらない子どもに共通する姿のように見受けられます。
自分自身の経験から探ると
僕自身、とりわけ中学生の頃はよく寝ていました。ベッドに入ってぐっすり寝るのではないのです。机の前でうたた寝です。自分の部屋に入ると、勉強をしないといけないことはわかっていながらも、すぐに睡魔がやってきていました。激しいスポーツをしていたわけではありません。なのに、いつも疲れていて、ぼんやりしているのです。大人になってこの現象を自分なりに理解したことは、次のようなことです。
演じる子は疲れる
僕は、親の前で演じる子どもでした。親の期待通りに生きようとしていました。日常の小さいことで言えば、親が顔をしかめた瞬間、それが何を意味しているかを察知し、その無言の要望を満たそうと心がけている子どもでした。だから、常に親の機嫌に敏感で、機嫌を損なわないような言動を意識していました。自分の意識は自分には向かず、親に向いていたのです。
このことを、親の視点から見て見ましょう。親は子どもの感情を抑圧し、自分の機嫌を優先していたのです。お行儀よくしなさい、大人しくしておきなさい、言わなくても勉強するよね?などが親の気持ち。そんな一言で子どもは動じないと思うかもしれません。1回や2回ならなんてことないかもしれません。

しかし、幼少期からの常態化していたのだろうと、これは明確な記憶はありませんが、漠然と思い出します。昭和のことですから、暴力も伴った経験も記憶にあります。子どもは、親の言う通りにしなければ、暴力をふるわれる、出ていけ!と言われる。これは恐怖です。なぜなら、無意識のうちにも、親が衣食住つまり、生命を守ってくれているから安心して生きることができているのに、その親に愛されなくなると自分の明日がないと知っているからです。生命を脅かすほど極端なことはないかも知れませんが、親にそのままの自分を愛してもらえない、それを表現することを許されていないことは、精神的な恐怖です。自我にとっては生死を意味する恐怖であることには変わりありません。
子どもは、親の要求通りにできないとなると、それでもその親に愛されたいから、できたフリをするのです。または、その要求に反発心を覚えても、反発をすると先に親の負の感情が襲ってくると繰り返し学習をしているなら、反発をしていないフリをするのです。つまり、演じることを徹底するのです。これが疲れの原因です。親に愛されたいから言う通りにしたい。でも、その内容は自分の素直な気持ちの結果ではなく、抑圧され、押し付けられたものだ。本当は嫌だ、でも親には嫌と言えない!「いい子」でいたい。相反する欲望に引き裂かれるように、エネルギーは真反対に引っ張り合い、自分の気持ちがどっと疲れる。僕のうたた寝は、これが理由だと思ったのです。
自分の気持ちが言えない子
反抗すればいいじゃないか、嫌だと言えばいいじゃないか。こう言える人は、幸せな幼少期を過ごした人です。親が、自分の素直な気持ちを受け止めてくれていたのです。親の意に反することを言っても、怒られずにいた子どもです。親の希望や感情を押し付けられなかった子どもです。
親に自分の気持ちが言えない子どもは、言えないなりの理由があったのです。つまり、言うと怒られたり、嫌な顔をされたり、そもそも言う前に親の要望や指示命令が飛んできたり。
例えば、勉強をしなさいと親が子に言うとします。イヤイヤやっている子は、本当は別のことがしたかったのだと僕は見て取ります。その本当にしたかったことがゲームとしましょうか。親としては、これ以上して欲しくない。だから勉強をしろと言った。親の主張は一理あると思います。しかし、そこでまず考えたいことは、子どもの気持ちと親の気持ちの整理です。これを、親の力でねじ伏せてはいけない。
「上下関係」を子どもに覚えさせるな
力や声の強さ、大きさでねじ伏せるのは、親が子よりも体格的に体力的に強いと思っているからです。自分が子どもの上に立てると思い、子どもは下に見ているのです。ゲームをやめて欲しい親心は子どもの心身の健康への配慮からだとしても、その配慮の良し悪しとは別に、親子関係で上下関係をやってしまうことに、非常に大きな心の問題が潜んでいます。これは、僕が経験し、嫌と言うほど大人になってからも悩んだことの一つです。身をもって声を大にして強調したいところです。
対等にいこう!
では、どうしろと言うのか? という親御さんの声が聞こえてきそうです。本当に子どもを愛する親なら、まずは、子どもの気持ちを言わせることです。そして「そうなのね」とそのままを受け止めることです。その内容の良し悪しは、それからのこと。まずは、受け止める。それから「なぜそうしたいの?」「それはいま、やらないといけないことなの?」と対話が始まる。その結論は家庭ごとにそれぞれでしょう。大切なことは、子どもの「いまの気持ち」を「言わせて」「受け止める」こと。これが対等な関係です。このステップをショートカットして、力でねじ伏せると、子どもは親子関係から上下関係が心に刻まれます。その刻み込まれた意識は、その子の生涯を左右する力を持っています。その子が自分で気づいて修正を試みるまで、ずっと。気づかない人は、80歳になっても人間関係は上下関係だと信じて疑いません。
上下関係に毒された子どもは、それでも負けたくありませんから、負けを別の行為でキャンセルしようとする。誰かもっと弱い子どもをいじめたり、黙って意地悪をしたり、皮肉的なことばかりを言ったり、嘘をついたり、去勢を張ったり、権力を悪戯に欲しがったり、お金に対する行き過ぎた姿勢に出ることもあります。法を犯すこと(やネット上の知らない誰かを無防備に信頼してしまうこと)だって、その延長には十分考えられることです。
そのままを受け止めることが愛
「そうなのね」と受け止める。これは、親子関係で愛を育んでいるのです。子どものありのままの姿を受け止め、目をかけてやる。これは大いなる愛です。勉強している姿しか愛さない、ヤンチャではなく大人しくしている姿しか愛さない、これは愛ではなく、親の都合であり、エゴです。そのエゴの押し付けを上下関係でやられた子どもは、いとも簡単にその親に屈します。親に愛されないと自分の衣食住が危ういし、親に愛されたいからです。親に愛されるために、屈したフリをする。常に抑圧状態の子どもは疲れ切ります。そして屈した心は、さらに屈折した言動を呼ぶ。「そうしないと居れない」という衝動を伴ってそれは現れます。
対等な親子関係、なんでも言いあえる親子関係が、子どもの心を愛情で満たします。そのままの自分を愛してくれているという実感が湧くからです。その安心感の上に、子どもはじっくりとものを考え、学習に向かうことができます。学習のできない子は、そこがいつもbusyで、感情を抑圧する親にエネルギーを吸い取られているのです。
おわりに
勉強のできない子の原因を、意識の散漫さに見て取り、その原因を葛藤によるエネルギーの消耗だと僕は結論を持ちました。自分の経験上のことですから、一つの見方に過ぎません。「いい子」は今日も静かに机の前に座っています。学校では先生の指導対象とはなににくく、放っておかれることの多い生徒だと思います。いい子はいい子なりに疲れて、意識の焦点が合いません。学習に対しても同じことです。親が、子どもの気持ちをそのまま言わせる、受け止めてやる。これが軌道修正の第一歩だと思います。これまでの習慣を変えることは時間と労力がかかります。今日の明日には変わることはありません。粘り強くいくしかありません。愛する我が子のためにできることは、そんなに多くないのですから、ぜひそうしてみませんか。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。自分の気持ちの言語化が苦手な方には、こんな記事もぜひお読みいただきたいと思います。
いい香りとともに自分の気持ちと向きあってみませんか



この記事をyou tubeでもご視聴いただけます。「言葉と気持ち…『香山先生』」ぜひチャンネル登録もお願いいたします!
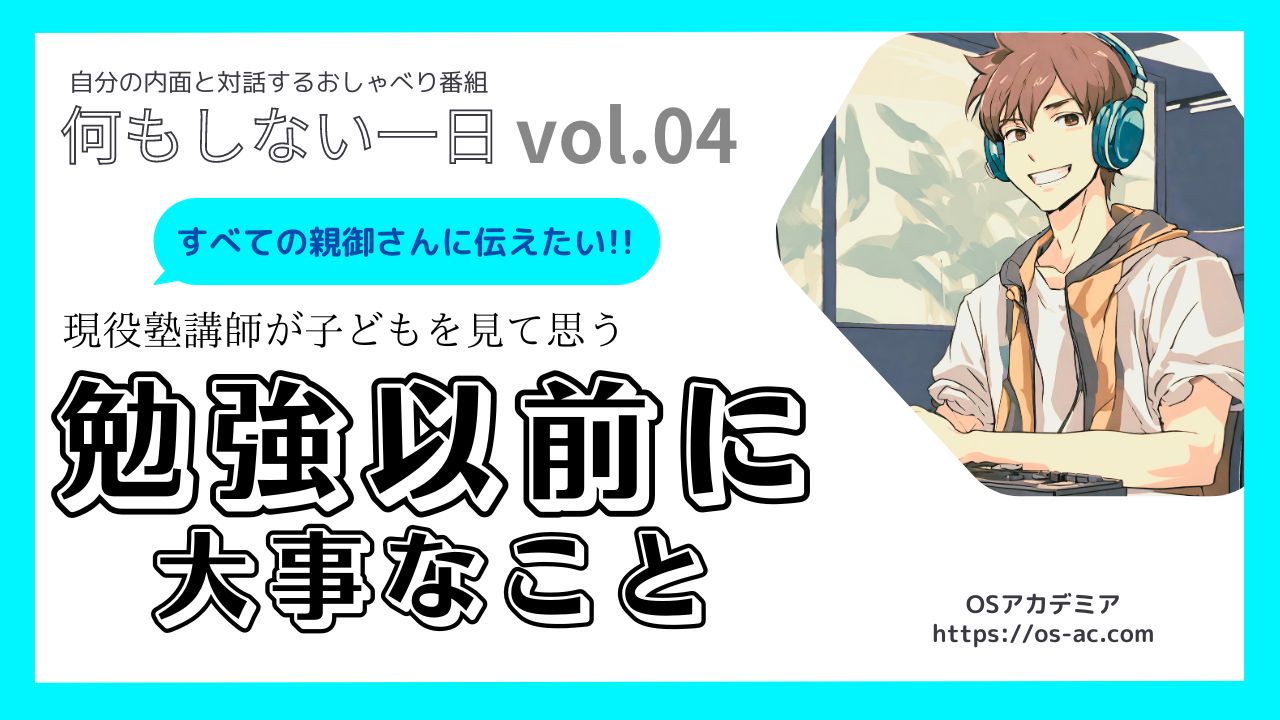

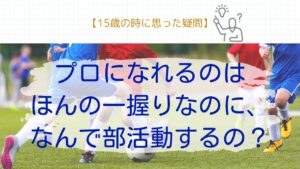

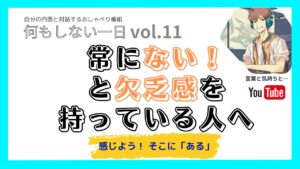
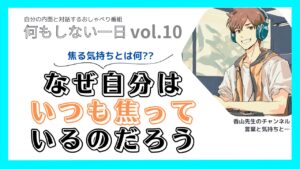
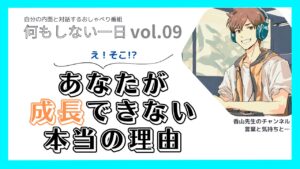
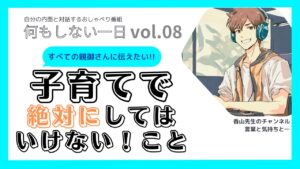
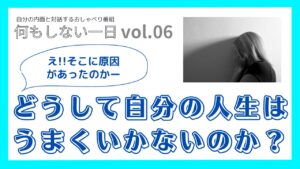
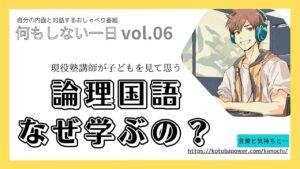
コメント